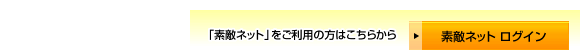プロに聞く 大規模修繕のツボ
大規模修繕工事の着工前に行うこと 〜工事契約から着工まで〜
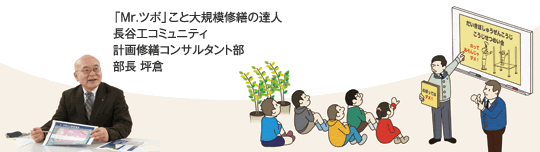
前回の本誌51号では大規模修繕工事の施工会社を選定し、総会議案にかけて決議を得るまでのプロセスをご紹介しました。今回は実際に工事に着手するにあたり必要となる、工事契約の締結から各種手続きなどの着工前準備についてご説明します。
工事契約
STEP 1 工事請負契約の締結
工事会社から提出された工事請負契約書の内容についてチェックを行い、契約当事者双方の合意の上、正式に契約を締結します。契約書のチェックは契約当事者である管理組合が行いますが、コンサルタントを入れている場合はコンサルタントと管理組合で行います。
《Point》
契約書には必ず記載すべき項目があり、それらの項目が全て当初の設計通りに記載されているかを確認します。
①発注者名、請負者名、工事名の他、何に基づいての契約なのかの記載と添付(例:工事契約約款、見積要領書、工事仕様書、見積書、図面、質疑回答書などの設計図書)
②工事場所
③工期(着工日、竣工日)と引渡日
④請負代金の額および支払条件とその時期
⑤その他特記すべき項目(工事保証に関する項目、アフター点検など)
⑥発注者・請負者双方の記名捺印(完成保証を付ける場合は完成保証会社を請負者に含める)
工事着工までの準備
工事契約締結から着工までは最低約1.5カ月の準備期間が必要です。ここでは、以下に挙げる主な項目の他、施工者選定時のヒアリングで約束したことが反映された計画なのかどうかも確認します。
STEP 2 仮設計画
工事会社からヒアリング時に提出された仮設計画に沿って現場事務所、休憩所、便所、資材置場、工事車両の進入路・駐車場等が当初の計画でよいのか、関係法規に則ったものであるか等を管理組合・監理者がいる場合は監理者と工事会社で協議し、最終決定します。
《Point》
【①届出の必要な項目は定められた期限までに届け出る】
工事会社は、足場を設置する場合に必要となる機械等設置届けを労働基準監督署へ足場の組み立て開始の30日前までに届出ます。これが、着工までの準備期間が1.5カ月以上必要なわけです。工事によっては他の届出や申請が必要なものがあります。
【②居住者の生活に配慮した計画】
たとえば住戸から見通せるような仮設トイレや居住者の動線を塞ぐような資材置場の配置は避け、子どもたちの登下校時には工事搬入車両の出入りを制限するなど、生活にできるだけ支障のない工事を行うよう配慮してもらいます。
【③足場周辺のセキュリティ対策】
足場の設置でマンションの2階以上の階でも不法侵入のリスクが高まるため、仮設計画には防犯上の配慮が必要です。足場の最下段を鉄製の網で囲い、夜間は施錠、階段を外すなどが標準的な方法ですが、機械警備システムの導入も効果的です。

STEP 3 施工計画
工事会社が作成した施工計画(施工方法、使用材料等)の内容が工事仕様書に沿ってつくられているか、施工手順や適切な材料・構造のものであるかなどを確認します。監理者がいる場合は監理者が確認し、管理組合が承認します。
STEP 4 工程確認
工事会社が作成した、いつ・どの部分を・どのくらいの期間で施工するかといった工程計画が、当初の工事計画期間内に無理なく終えられるものであるか確認します。監理者がいる場合は監理者が確認し、管理組合が承認します。
STEP 5 対応窓口の設置
工事中の居住者のお困りごとに対する窓口の設置や工事中の各種広報の仕方、居住者側が協力すべき項目とその対処方法などを、管理組合(監理者がいる場合は監理者も含め)が工事会社と協議して定めます。

《Point》
居住者側が協力すべき項目は、たとえばバルコニーの植木の移動や網戸を取り外して室内での保管などがあります。植木は仮設の植木置き場を敷地内に工事会社に設置してもらい、水やりなどの管理は居住者各自で行うのが一般的です。網戸の場合は、有償ですが取り外して網の張り替えと工事中の保管をして工事に差し支えない時期に復旧してくれるサービスもあります。

工事説明会の開催
STEP 6 居住者への工事説明会
Step1〜5までを決定した後、居住者への工事説明会を行います。工事成功のためには居住者の協力が欠かせないため、理解を得られるよう具体的に工事内容を説明し、質疑応答などを行います。
《Point》
子どもが多いマンションは子ども向けの説明会も並行開催するのも良いでしょう。